
日本が国連の常任理事国になる?
昨日、バイデン大統領と岸田首相が会談して、非常に多くのテーマについて語りあったということです。 ・ウクライナ問題とプーチンの責任追及 ...

昨日、バイデン大統領と岸田首相が会談して、非常に多くのテーマについて語りあったということです。 ・ウクライナ問題とプーチンの責任追及 ...

日本以外の諸国は、全て平和を愛する優しい国だから、日本の安全を委ねようということです。このような歯の浮くような文言が憲法の最初に出てきます。この文言と日米安全保障条約は矛盾します。アメリカ以外の諸国の国民の公正と信義を信頼していないからです。

日本国憲法は、第9条以外にも多くの問題があります。その世界観・思想的背景が滅茶苦茶なのです。

いま唱えられている日本国憲法無効説は、どれも理論的に少し無理があります。それも当然で、もともと無効な憲法をあたかも成立していたかのように扱っ...

日本国憲法が無効だとしたら、現実を規制している法律の根拠がなくなります。多くの日本人はそれを心配して、日本国無効説を認めようとしません。だか...

「日本国憲法など存在していないのだ」ということが日本中の常識になったら、日本人は、「では日本の今の状態はどうなっているのだ」と考え始め、ちゃんとした憲法を作ろうとし始めるはずです。
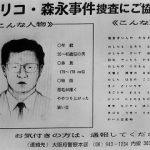
法理論的には、「日本国憲法無効説」が正しいのです。だから、アメリカの占領が解除された当時は、無効説が有力でした。しかし一旦、有効に成立したと...

大日本帝国憲法の改正手続きは無効なので、大日本帝国憲法を改正したものと称する日本国憲法は存在しません。私だけでなく、多くの人も同じように考え...
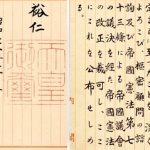
実は、日本国憲法は大日本帝国憲法を改正した、という形式になっています。大日本帝国憲法の第73条では、貴族院と衆議院のそれぞれで、三分の二以上の賛成があれば、憲法改正が出来るとさだめているのです。しかし、これは、法律論として無理があり、常識にも反します。

当時の日本人は、「戦争に負けた」という実感は十分すぎるほど持っていました。しかし、憲法を巡って内乱が起きたり、暴動が起きたりという「てんやわんや」の状況などは全くなく、毎日生き延びるのに必死なだけでした。